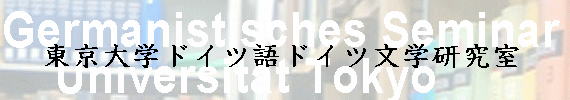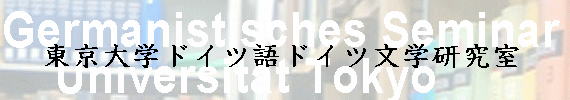第93号
■ ノヴァーリスの国家論
その可能性と限界
… 平井 涼(1)
Ryo HIRAI: Novalis´ Staatstheorie
Ihre Potenziale und Gefahren
■ 容器とゲシュタルト
『静かなヴェロニカの誘惑』における閉鎖空間
… 五十嵐 遥也(51)
Haruya IKARASHI: Gehäuse und Gesatlt
Geschlossene Räume in Robert Musils
Die Versuchung der stillen Veronika
■ 芸術作品はいかにして野蛮となるか
トーマス・マン『ファウストゥス博士』における
ニーチェ批判とアドルノ音楽論の交点
…渡邊 能寛(75)
Takahiro WATANABE: Wie verfällt das Kunstwerk der Barberei?
Über das Wechselverhältnis zwischen Thomas Manns Nietzsche-Kritik
und der Musikphilosophie Adornos im
Doktor Faustus
■ 「子どもである」わたしへ
ペーター・ハントケ作品における子どものモティーフについて
…八木 頼子(99)
Yoriko YAGI: Der Erwachsene und das Kind
Peter Handkes Kindermotivik
第92号
■ 悪徳の支配
――『阿呆物語』にみる愚と罪――
… 森下 勇矢(1)
Yuya MORISHITA: Dominierende Laster
Sündhafte Narrheit in Grimmelshausens
Simplicissimus Teutsch
■ 脱主体化の映画学
フーコーの装置論とベンヤミンの遊歩・映画論
…菅谷 優(21)
Yu SUGAYA: Dispositiv bei Foucault und Kino/Flanieren bei Benjamin.
■ クリスタ・ヴォルフと「病」
『クリスタ・Tの追想』における混沌と探求の語り
… 中村 祐子(53)
Yuko NAKAMURA: Chirsta Wolf und Krankheit
Chaos und Suche in
Nachdenken über Christa T.
第91号
■ 好奇心と破滅
『実伝ファウスト博士』にみる愚者概念
… 森下 勇矢(1)
Yuya MORISHITA:
Curiositas und Verderben
Zur Narrenidee im
Historia von D. Johann Fausten
■ 生/身体/芸術
ノヴァーリス思想の生成と構造(二)
… 平井 涼(21)
Ryo HIRAI: Leben/Körper/Kunst
Zur Entwicklung und Struktur von Novalis’ Denken (2)
■ キネマトグラフの比喩
──ローベルト・ムージルにおける仮想的連続性のイメージ──
… 五十嵐 遥也(125)
Haruya IKARASHI: Die Kinematograph als Metapher
Robert Musils Vorstellung von der virtuellen Kontinuität
■ フランツ・カフカの一人称複数形“私たち”
――初期の日記から中期発表作品まで――
… 三根 靖久(145)
Yasuhisa MINE: Zum „Wir“ in Franz Kafkas frühen Tagebüchern
bis zu den veröffentlichten Erzählungen des Bandes
Ein Landarzt
■ アンナ・ゼーガース『死者はいつまでも若い』における
ナチズムとコミュニズム、反ナチズムの相克
… 中原 綾(179)
Aya NAKAHARA: Die Konfrontation von Nazismus und Kommunismus
in
Die Toten bleiben jung von Anna Seghers
■ 接ぎ木する詩人
パウル・ツェランの園芸的詩作について
… 山中 慎太郎(199)
Shintaro YAMANAKA: Dichter/Pfropfer
Über die gartenkünstlerische Dichtung von Paul Celan
■ Christa Wolf und ‚Krankheit‘
Weibliche Entscheidungsmuster in
Der geteilte Himmel
… Yuko NAKAMURA(219)
■ 試訳と解題:ヴェルナー・ハーマッハー遺稿集より
「未完のヘルダーリン論からのパサージュ二選」(前半)
… 平野 遥海・若山 真理子(249)
Harumi HIRANO・Mariko WAKAYAMA: Aus dem Nachlass von Werner Hamacher: „[Zwei Passagen aus einer nicht geschriebenen Hölderlin-Arbeit]“.
Eine erste Übersetzung und Kommentar, Teil 1.
第89号
■ Erbaulicher Pikarismus
Zum Verhältnis zwischen satirischen und frommen Elementen in Grimmelshausens „Simplicissimus Teutsch“
… Yuya MORISHITA(1)
■ 諸学の体系化と哲学の意義
ノヴァーリス思想の生成と構造(一)
… 平井 涼(17)
Ryo HIRAI: Die Systematisierung der Wissenschaften und die Bedeutung der Philosophie
Zur Entwicklung und Struktur von Novalis’ Denken (1)
■ アンナ・ゼーガース „Der Kopflohn“ における「あきらめる者」と
「ゆれる者」の形象
… 中原 綾(139)
Aya NAKAHARA: Die Figuren des Resignierenden und des Schwankenden in Anna Seghers’
Der Kopflohn
■
境の文学
古井由吉の「ドゥイノ・エレギー訳文」
… 菅谷 優(169)
Yu SUGAYA: Dichtung der Schwelle / Grenze
Zu Yoshikichi Furuis Übersetzung von Rilkes Duineser Elegien
第88号
■ フケーの近代性
――『ロサウラとその一族』における戦争の表現を中心に――
… 伊藤 貴康(1)
Takayasu ITO: Modernität in Fouqués Erzählungen
Über die Behandlung des Kriegs in
Rosaura und ihre Verwandten
■
語り手の眼差し、語り手への眼差し
―フランツ・カフカ『新人弁護士』と『ある学士院への一通の報告書』
… 三根 靖久(17)
Yasuhisa MINE: Blicke des Erzählenden, Blicke auf den Erzählenden
Franz Kafkas
Der neue Advokat und
Ein Bericht für eine Akademie
■ Brecht und die antike Tragödie
Über seinen Versuch der Ent-Tragödisierung von Sophoklesʼ
Antigone
… Fumi OKANO(59)
■ 損傷した物語
――ゲアハルト・フリッチュ『ファッシング』における断片性の詩学
… 前田 佳一(87)
Keiichi MAEDA: Das beschädigte Erzählen
― Gerhard Fritschs Poetologie der Fragmentarität
■ 変貌する Schattentheater
ミヒャエル・エンデ『オフェリアの影の一座』論
… 三好 鮎子(101)
Ayuko MIYOSHI: Die Verwandlung des Schattentheaters
Zu Michael Endes
Ophelias Schattentheater
第87号
■ 愚のペルソナと大阿呆の死
トーマス・ムルナー『ルター派の大阿呆』にみる謝肉祭要素
… 森下 勇矢(1)
Yuya MORISHITA: Narren-Persona und der Tod des großen lutherischen Narren.
Fastnächtliche Elemente in dem Thomas Murners
Von dem grossen Lutherischen Narren.
■
自己投影的な形容と対象の行方
E・T・A・ホフマンの『G市のイエズス会教会』における描写不可能という形容
… 堀 弥子(31)
Hisako HORI: Subjektive Beschreibungen
Schilderungen wie „unbeschreiblich“ in E. T. A. Hoffmanns
Die Jesuiterkirche in G.
■
旅の認識
デーブリーン『ポーランド旅行』における宗教とパノラマ
… 正月 瑛(51)
Aki SHOGETSU: Erkenntnis (in) der Reise
Über die Religionen und Panoramen in Alfred Döblins
Reise in Polen
■
声の飛翔/地への陥入
ストローブ=ユイレ『アンティゴネー』――民の不在
… 菅谷 優(73)
Yu SUGAYA: Aufflug der Stimme / Versinken in die Erde
Antigone von Straub-Huillet, Leerstelle des Volkes
第86号
■ ガーヴァーンの秘密主義とtriuwe
―宮廷の美徳のジレンマとパルチヴァールによる解決―
Aya MATSUBARA: Gawans Heimlichkeiten und
triuwe
Das Dilemma der höfischen Tugenden und Parzivals Lösung
......松原 文(1)
■ ノヴァーリスのフィヒテ批判は妥当しているか(下)
フィヒテ『全知識学の基礎』を中心に
Ryo HIRAI: Trifft Novalis' Kritik an Fichte zu? (3)
Hauptsächlich über Fichtes „Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre“
......平井 涼(25)
■ とどめえぬ「優美」
E. T. A. ホフマン『従兄の隅窓』における「語り」について
Hisashi SHIMIZU: Die unaufhaltsame/unbeschreibliche Anmut
Über das Erzählen in E. T. A. Hoffmanns
Des Vetters Eckfenster
......清水 恒志 (123)
■ イメージの言語 vs. 身体の言語
―ホーフマンスタール『手紙』における境界の出現―
Nachi ISHIBASHI: Sprache der Bilder vs. Sprache des Körpers
Die Vergegenwärtigung der Grenze in Hofmannsthals
Ein Brief
......石橋 奈智 (151)
■ Reflexion über die Versprachlichung der Ortsveränderung (1)
Exposition der Fragestellung
......Tomomi SHIRAI (169)
第85号
■
ヘッセのアメリカ/アメリカのヘッセ―素描
Kanichiro OMIYA: Hesses Amerika/ Amerikas Hesse - eine Skizze
......大宮 勘一郎 (1)
■
<労働者>は語ることができるか
デーブリンの諸テクストにおけるマルクス(主義)
Aki SHOGETSU: Can the Arbeiter speak? Marx(ismus) in Texten Alfred Döblins
...... 正月 瑛 (15)
■
クラカウアーの大衆光学
―人間存在への眼差し―
Kazuki FUKAZAWA: Kracauers Massen-Optik
Eine anthropologische Relektüre seiner Essays
...... 深澤 一輝 (37)
第84号
■ ヴィーラント『アガトン物語』からゲーテ『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』へ
『アガトン物語』における「新しさ」
Azusa TAKATA: Von Wielands Geschichte des Agathon bis Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre ― „Die Neuheit" in Wielands Geschichte des Agathon
......髙田 梓(1)
■ ノヴァーリスのフィヒテ批判は妥当しているか(中)
フィヒテ『全知識学の基礎』を中心に
Ryo HIRAI: Trifft Novalis‘ Kritik an Fichte zu? (2)
...... 平井 涼(19)
■
モンタージュの射程
デーブリーン『ベルリン・アレクサンダー広場』とその方法
Aki SHOGETSU: Die Tragweite der Montage
Alfred Döblins »Berlin Alexanderplatz« und seine Methode
......正月 瑛(99)
■
Nerven auf dem Rad
Innervation bei Benjamin, auf die Kinematographie bezogen
......Yu SUGAYA(125)
■ E. ユンガーの『痛みについて』に関する考察
Sumiko IIDA: Betrachtungen zu Ernst Jüngers Über den Schmerz
......飯田 澄子(149)
第83号
■ 重藤実教授 略歴
Lebenslauf und Veröffentlichungen von Minoru Shigeto
......(1)
■ ドイツ語標準語と辞書
Minoru Shigeto: Deutsche Hochsprache und Wörterbücher
......重藤 実(9)
■ Beschreibung der deutschen Aussprache und das „Deutsche Aussprachewörterbuch“ von Eva-Maria Krech et al.
......Minoru SHIGETO(17)
■ドイツ語の否定表現の通時的変化
― nicht、kein、否定のサイクル ―
Maiko NISHIWAKI: Zur Diachronie der Negation im Deutschen
― nicht, kein und Negationszyklus ―
......西脇 麻衣子(27)
■ ノヴァーリスのフィヒテ批判は妥当しているか(上)
フィヒテ『全知識学の基礎』を中心に
Ryo HIRAI: Trifft Novalis‘ Kritik an Fichte zu? (1)
...... 平井 涼(45)
■
曖昧な語り
E・T・A・ホフマンの短編『サンクトゥス』における暗示的表現
Hisako HORI: Vages Erzählen
Zum andeutenden Stil in E. T. A. Hoffmanns Nachtstück Das Sanctus
......堀 弥子(87)
■ 大都市への恐怖と礼賛
パウル・ボルトの詩「カフェ・ヨスティのテラスにて」
Atsuhiro HINA: Furcht und Ehrfurcht vor der Großstadt
Über Paul Boldts Gedicht Auf der Terrasse des Café Josty
......日名 淳裕(121)
■方法としての「拡散」
―ベンヤミンとクラカウアーにおけるその射程―
Kazuki FUKAZAWA: Zerstreuung als Methode
Ihre Tragweite bei Walter Benjamin und Siegfried Kracauer
......深澤 一輝(139)
■クリスティアン・クラハト『ファーザーラント』における世代の表象
―世代間抗争の主題と教養小説としての再考―
Azusa TAKATA: Das Bild einer Generation in Christian Krachts Faserland
Generationskonflikt/-wechsel und Möglichkeit als Bildungsroman
......髙田 梓(165)
第82号
■ ゼレーヌス書簡
『黄金の壺』作者への匿名書簡
Toshimi OMATA: Der Brief des Serenus an den Verfasser der Fantasiestücke
…小俣 登糸美(1)
■ 優美の現場
―ルーモールの『料理術の精神』―
Yoshio TOMISHIGE: Über den Anmut-Begriff im „Geist der Kochkunst“ von
Carl Friedrich von Rumohr
… 冨重 与志生(21)
■ トーマス・マン『衣装戸棚』
―隠された欲望の語りについて―
Mayuko KIDO: Thomas Manns Erzählung Der Kleiderschrank
Das Erzählen des verheimlichten Begehrens
… 木戸 繭子(41)
■
カフカの眼
Aki SHOGETSU: Kafkas Auge(n)
… 正月 瑛(65)
■ 初期ベンヤミンにおける理論構造の生成と源泉(三)
Ryo HIRAI: Die Genese und Quelle der theoretischen Struktur beim frühen Benjamin (3)
… 平井 涼(91)
■ 日記の私
――ローベルト・ヴァルザーの『〈日記〉』について――
Takayuki KASAI: Das Ich im Tagebuch
Über Robert Walsers sogenanntes „Tagebuch“
… 葛西 敬之(125)
■ Ein Kind ohne Mutter. Ilse Aichingers „Die größere Hoffnung“
… Yoriko YAGI(147)
第81号
松浦純先生 略歴
Lebenslauf und Veröffentlichungen von Jun Matsuura
......(1)
■ 身体vs.言語 ―ドイツ中世トリスタン物語の意匠
Die letzte Vorlesung von Jun Matsuura
...... 松浦 純(7)
■ Die Weimarer Ausgabe als editorische Leistung
– aus der Erfahrung der Neuedition von Luthers frühen Randbemerkungen
...... Jun Matsuura(53)
■ 『ディートリヒの逃亡』における「作者」像
―ジャンル交差の諸相から
Jun YAMAMOTO: Das Autorbild in „Dietrichs Flucht“. Reflexionen über Gattungsinterferenz.
...... 山本 潤(61)
■
告白される分身
E・T・A・ホフマン『悪魔の霊液』試論
Hisako HORI: Der Doppelgänger als Erzählgegenstand
Zu den Elixieren des Teufels von E. T. A. Hoffmann
...... 堀 弥子(91)
■ 楽士長ヨハネス・クライスラーの人生観
E. T. A. ホフマン『牡猫ムルの人生観』――「猫」の教養小説――(2)
Hisashi SHIMIZU: Lebens-Anschauung des Kapellmeisters Johannes Kreisler
E. T. A. Hoffmanns „Lebens-Ansichten des Katers Murr“ Des „Katers“ Bildungsroman (2)
...... 清水 恒志(113)
■ Ich und/als ein heißer Brei
―ローベルト・ヴァルザーの「私」について―
Takayuki KASAI: Ich und/als ein heißer Brei
Über Robert Walsers Ich
...... 葛西 敬之(139)
■ 初期ベンヤミンにおける理論構造の生成と源泉(二)
Ryo HIRAI: Die Genese und Quelle der theoretischen Struktur beim frühen Benjamin (2)
...... 平井 涼(159)
■
埋められた希望
―シュテファン・ツヴァイクのユダヤ伝説における故郷喪失とシオニズム―
Yukiko SUGIYAMA: Die begrabene Hoffnung
Heimatverlust und Zionismus bei der jüdischen Legende Stefan Zweigs
...... 杉山 有紀子(193)
■
絵を描くムーミンママ
トーベ・ヤンソン『パパと海』における女性の芸術と自己実現
Teiko NAKAMARU: Die Muminmama malt sich
Selbstverwirklichung der Künstlerinnen in Tove Janssons Der Papa und die See
...... 中丸 禎子(213)
第80号
■ German Screenwriters in Hollywood,
1914–45
A Comparison between Emigration and Exile… Stefan
KEPPLER-TASAKI(1)
■ 助言者トリフリツェントによる偽りの告白
―『パルチヴァール』における誠〈triuwe〉の一側面― … 松原 文(23)
Aya MATSUBARA: Ratgeber Trevrizents Geständnis
seiner Lüge
Eine Interpretation von triuwe in Parzival
■ マイスター・アブラハムの修業時代
E. T. A. ホフマン『牡猫ムルの人生観』―「猫」の教養小説―(1)…清水 恒志(41)
Hisashi SHIMIZU: Meister Abrahams Lehrjahre
E. T. A. Hoffmanns „Lebens-Ansichten des Katers Murr“
Des „Katers“ Bildungsroman (1)
■ インシュテッテンの幽霊
―フォンターネ『エフィ・ブリースト』における幽霊表象―…五島 萌(67)
Moe GOTO: Innstettens Spuk
Zum Gespenster-Symbolik in Fontanes Effi Briest
■ Walser tanzt mit Kleist
―ローベルト・ヴァルザーのクライスト受容― … 葛西 敬之(91)
Takayuki KASAI: Walser tanzt mit Kleist
Zur Kleist-Rezeption Robert Walsers
■ 初期ベンヤミンにおける理論構造の生成と源泉(一) … 平井 涼(113)
Ryo HIRAI: Die Genese
und Quelle der theoretischen Struktur beim frühen Benjamin (1)
■ 繰り返しと言葉の音楽化
バッハマン「アクラガス河畔」にみるトラークルの影響… 日名 淳裕(143)
Atsuhiro HINA: Wiederholung und Musikalisierung
der Sprache
Untersuchung zum Einfluss Trakls auf Bachmanns
Gedicht Am Akragas
第79号
梶原 将志
ヴィーラントの歌唱劇『ミダスの審判』について
―〈すでに-在る〉美と《演劇的なもの》との角逐―
Masashi KAJIWARA: Zu Wielands
Singspiel »Das Urteil des Midas«– Konflikt zwischen der Schönheit, die schon
da ist, und dem „Dramatischen“ –
清水 恒志
『ルツィンデ』のアラベスク
―文体の試行と「子供の死」―
Hisashi SHIMIZU: Die Arabeske
der „Lucinde“ Die Erprobung des Stils und der Tod der Kinder
杉山 有紀子
モンテーニュ、ツヴァイクと自己叙述のダイナミズム
―『エセー』の著者についてのエッセイをめぐる随想的試論―
Yukiko SUGIYAMA: Montaigne und
Zweig: die Dyamik der Selbstdarstellung
Ein essayistischer Versuch zum Essay über den
Autor der Essais
日名 淳裕
フィッカー、ツェラン、ハイデガー
―オーストリア戦後抒情詩の展開とトラークル像の変遷―
Atsuhiro HINA: Ficker, Celan,
Heidegger Entwicklung der österreichischen Nachkriegslyrik und das Trakl-Bild
nach 1945
第78号
中丸 禎子
森鷗外の北欧受容― ラーゲルレーヴ『牧師』の翻訳 ―
Teiko NAKAMARU: Mori Ogais Rezeption der nordischen Literatur ― Die Übersetzung von Selma Lagerlöfs Der Prediger―
木戸 繭子
つばめと幸福な王子、あるいは男爵夫人アンナ
― トーマス・マン『ある幸福』について ―
Mayuko KIDO: Die Schwalbe, der gl
ückliche Prinz und Baronin Anna
― Über Thomas Manns Erzählung Ein Glück―
日名 淳裕
George und
Hofmannsthal revisited ― 詩「ふたり」と『盟約の星』―
Atsuhiro HINA: George und Hofmannsthal revisited ― "DIE BEIDEN" und Der Stern des Bundes―
葛西 敬之
ローベルト・ヴァルザーの散文の表層性について
Takayuki KASAI: Über die Verwahrlosung von Robert Walsers Prosa
飯田 澄子
E. ユンガーの『労働者』についての考察
―ハイデガーの「芸術作品の根源」に対する影響に関する試論―
Sumiko IIDA: Zu Ernst Jüngers Der Arbeiter mit besonderer Berücksichtigung von dessen Einfluss auf Heideggers Kunstwerk-Aufsatz
第77号
山崎 泰孝 Yasutaka YAMASAKI
リルケ『オルフォイスへのソネット』における時間性
Zeitlichkeit in Rilkes
Sonetten an Orpheus
杉山 有紀子 Yukiko SUGIYAMA
シュテファン・ツヴァイク『ロッテルダムのエラスムスの勝利と悲劇』試論―自由のイデオロギー化とヒューマニズムの問題をめぐって―
Stefan Zweig:
Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam – Gegen die Ideologisierung der Freiheit–
Atsuhiro HINA
FRANZ FÜHMANNS TRAKL-REZEPTION― Zur Entstehung
und Entwicklung des Essays Vor
Feuerschlünden. Erfahrung mit Georg Trakls Gedicht (1982) ―
第76号
Christine IVANOVIĆ
Das Maß der Hoffnung. Ilse Aichingers Zeitsprünge
杉山 有紀子 Yukiko SUGIYAMA
昨日の世界のヨーロッパ人 ― シュテファン・ツヴァイク『昨日の世界』とハンナ・アーレントによるその批評をめぐって ―
„Ein Europäer“ in der Welt von Gestern – Hannah Arendt über Die Welt von Gestern von Stefan Zweig –
日名 淳裕Atsuhiro HINA
Der Ort : gedicht ― Über Thomas Klings Gedicht mühlau,† ―
第75号
松原
文 Aya
MATSUBARA
『ニーベルンゲンの歌』におけるtriuwe ― クリエムヒルトの宝の要求に関する写本B・Cの相違を手がかりに ―
‚triuwe’
im Nibelungenlied –Überlegungen zu den Unterschieden zwischen den Handschriften
B und C bei Kriemhilds Hortforderungsszene –
梶原
将志 Masashi KAJIWARA
レッシング『悲劇に関する往復書簡』について ― 民衆教化と混合感情の両取り,レトリカルな帳尻合わせ ―
Zu Lessings Briefen über das Trauerspiel – Zwei Probleme und eine rhetorische
Lösung –
杉山 有紀子 Yukiko SUGIYAMA
ツヴァイク/シュトラウスのオペラ『無口な女』 ― 革命前夜の「非政治的」喜劇 ―
"Die Schweigsame Frau" von Stefan Zweig und Richard Strauss – Eine
„unpolitische“ Komödie am Vorabend der
Revolution –
日名 淳裕Atsuhiro
HINA
読み替えられた詩人 ― トラークル受容史におけるハイデガー「詩の中の言語」 ―
Der
umgeschriebene Dichter – Die Sprache im
Gedicht in der Rezeptionsgeschichte Georg Trakls –
第74号
中丸 禎子Teiko NAKAMARU
ドイツ民族主義と北欧 ―「郷土芸術運動」と「血と大地文学」における北欧文学の受容 ―
Völkischer
Nationalismus und Skandinavien – Die Rezeption der skandinavischen Literatuer in
der Heimatkunstbewegung und der Blut- und Boden-Literatur – ...................................................... .. 1
日名 淳裕Atsuhiro HINA
ゲオルク・トラークルの散文詩の位置 (2)― 散文詩『啓示と没落』と戯曲断片『小作人の小屋で...』草稿の比較分析 ―
Zur
Bedeutung des Prosagedichts bei Georg Trakl (2) – Eine vergleichende Analyse
der Entwürfe zweier gattungsverschiedener Texte: des Prosagedichts Offenbarung und Untergang und des
Dramenfragments In der Hütte des
Pächters… – ........................................................................................................
.17
杉山 有紀子 Yukiko SUGIYAMA
平和理念を「生きる」預言者 (2) ― シュテファン・ツヴァイクの「敗北主義」と自由理念について ―
Ein
Prophet, der seine pazifistische Idee lebt
(2) – Über Stefan Zweigs „Defaitismus“ und seine Idee der Freiheit – ....................................................................................................................................................35
時田 郁子 Yuko TOKITA
天球の音楽 ― ムージル『メロドラマ『黄道十二宮』への序曲』について ―
Die Sphärenmusik – Zu Musils Vorspiel zu dem Melodrama «Der Tierkreis»
– .....................................57
第73号
山本 潤 Jun YAMAMOTO
『哀歌』の「ニーベルンゲンの歌」に対する注釈的機能 ―「triuwe」と「übermuot」を巡って―
Die Funktion der Nibelungenklage als Kommentar zum Nibelungenlied -Zu den
Begriffen triuwe und übermuot-
|
1 |
|
|
日名 淳裕 Atsuhiro HINA
ゲオルク・トラークルの散文詩の位置(1) ―散文詩『啓示と没落』と戯曲断片『小作人の小屋で...』草稿の比較分析―
Zur Bedeutung des Prosagedichts bei Georg Trakl (1) -Eine vergleichende
Analyse der Entwürfe zweier gattungsverschiedene Texte: des Prosagedichts
"Offenbarung und Untergang" und des Dramenfragments "In
der Hütte des Pächters..." |
39 |
|
|
杉山 有紀子 Yukiko SUGIYAMA
平和理念を「生きる」預言者 (1) ―シュテファン・ツヴァイク『エレミヤ』における敗北の意義について
Eine Prophet, der seine pazifistische Idee lebt (1) -Über die Bedeutung der Niederlage in Stefan Zweigs Jeremias- |
57 |
|
|
前田佳一 Keiichi MAEDA
"...ich schreibe Ihnen in höchster Angst und fliegender Eile..."
―インゲボルク・バッハマンの時間経験について
"...ich schreibe Ihnen in höchster Angst und fliegender Eile..."-Ingeborg
Bachmanns "Ein Ort für Zufälle"
|
77 |
第72号
山本 潤 Jun YAMAMOTO
『ニーベルンゲンの歌』の重層構造―シーフリト像を中心に―
Mehrschichtigkeit des Nibelungenliedes -Die Figur Sîvrits als Beispiel-
|
1 |
|
|
梶原 将志 Masashi KAJIWARA
悲劇論と自己分析―シラー『メッシーナの花嫁』のコロスをめぐる諸言説について―
Tragödientheorie und Ich-Analyse -Zu Diskursen über den Chor in Schillers »Braut von Messina«
|
23
|
|
|
小野間 亮子 Ryoko ONOMA
アラベスクと円環―ホーフマンスタールのメールヒェンにおける中心点について―
Arabeske und Kreis -Über den ästhetischen Mittelpunkt in den Märchen von
Hofmannsthal
|
57
|
|
|
山崎 泰孝 Yasutaka YAMASAKI
リルケ『ドゥイノの悲歌』における天使への呼びかけ
Der Anruf des Engels in den Duineser Elegien |
75 |
|
|
時田 郁子 Yuko TOKITA
ムージルの詩的言語
Die poetische Sprache bei Musil |
89 |
|
|
前田佳一 Keiichi MAEDA
"Gebt uns neu. Gebt uns das Neue..."―バッハマン『偶然/発作のための場所』草稿の諸問題
"Gebt uns neu. Gebt uns das Neue..."-Probleme in der Textgenese
von Ingeborg Bachmanns "Ein Ort für Zufälle"
|
第71号
第70号
第69号
山村 浩 Hiroshi YAMAMURA
自我と超自我
Das Ich und das Über-Ich |
1 |
|
|
三根 靖久 Yasuhisa MINE
明かせない素姓―カフカ『審判』について
Die geheime Abstammung |
15 |
|
|
前田 佳一 Keiichi MAEDA
"... Ich möchte ein Ende mit dir, ein Ende. Und eine Revolte gegen
das Ende..."
インゲボルク・バッハマン『マリナ』における相続のプロセス(1)
Zum Prozess des Hinterlassens in Ingeborg Bachmanns Roman Malina (1) |
41 |
第68号
◆第67号 (2007.7)
■山本 潤:写本伝承段階における「ニーベルンゲンの歌」と「哀歌」の受容
■江口 大輔:ジャン・パウルの機知理論におけるBildについて
■清水 健吾:〈怪奇〉と〈驚異〉の両義性: E.T.A.ホフマンの『砂男』
■山村 浩:自己と価値―ニーチェと価値哲学―
■山崎 泰孝:リルケの『新詩集』における不在
◆第66号 (2007.3)
■Yoshihiko HIRANO:Auschwitz ― Berlin ― Ukraine. Einige
Kapitelanfänge zu einem kommenden Celan-Buch: „Toponym als U-topie“
■吉中俊貴:同時代のアンチ・ホームズ ― シュニッツラー『予言』論―
■山崎泰孝:色彩をめぐって ― ホフマンスタールの『帰国者の手紙』とリルケのセザンヌ書簡
■林崇宏:<私>をめぐるもう一つの戦い ― カフカ『ある戦いの記』二つの稿の比較
■野崎啓太:息子たちについて ― 『火夫』、『変身』を中心に ―
■鈴木里香:ユートピアへの夢 ― フランツ・カフカ『失踪者』における「演劇的なもの」をめぐって
■田中亜美:<石>のみちのり ― ツェラーンにおける死者たちの位相
◆第65号 (2006.7)
■藤井啓司:メクレンブルクの青い空
■平野嘉彦:藤井啓司さんを偲ぶ
■渡辺学:ヴィルヘルム・フォン・フンボルトとアジア諸言語 ― 1828年の英文書簡を手がかりに ―
■畠山寛:神・自然・時 ― ヘルダーリンにおける「悲劇」と「時」
■Toshiyuki YUI:
Schriftverkehr und Abkehr von den Schriften ― Zum Zettel-Motiv in Kleists Erzählung Michael Kohlhaas
■田中千裕:メルヒェンの世界・伝説の世界 ― グリム兄弟の『子どもと家庭のメルヒェン集』における「魔法昔話」と『ドイツ伝説集』における「土地伝説」比較
■吉中俊貴:無意味なものの物語化 ― シュニッツラーのノヴェレッテ『Ich』―
■Christine IVANOVIĆ: „…dass man von einer Frau nichts sagen könne.“ Ingeborg
Bachmanns Malina im Licht von Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Laurids
Brigge.
■村瀬民子:人形と天使 ― ハイナー・ミュラーの演劇における「視る」ことの題材化
■中丸禎子:無意味に貫かれた生 ― クリスタ・ヴォルフ『クリスタ・Tの追想』における「物語」の否定と「意味づけ」の拒否
■岩本剛:沈黙の音調 ― マルセル・バイアー『オオコウモリ』試論
◆ 第64号 (2005.12)
■畠山寛:ヘルダーリンの抽象名詞と詩の完成
■中村恵美子: Fr. シュレーゲルのアラベスク概念解明のために ― セルバンテスとスターンを中心として
■古矢晋一:群衆・境界・グロテスク ―
エリアス・カネッティにおける「グロテスクなもの」をめぐって ―
■吉中俊貴: 真空への吹き込み ―
物語理論から読むマルセル・バイアーの長編小説『オオコウモリFlughunde』―
◆ 第63号 (2005.7)
■田窪大介:レッシングの『ミス・サラ・サンプソン』と『エミーリア・ガロッティ』における徳の概念について
■吉中俊貴: 語り手の脱権威化―自律内的独白への物語理論的考察から―
■木戸繭子:『ブデンブローク家の人びと』―「永遠にして女性なるもの」をめぐって
■時田郁子:物語生成の場としての身体―ムージル『三人の女』について
■林崇宏:「私」をめぐる戦い ―カフカ『ある戦いの記』Fassung A について
■田中亜美:<息>のみちのり ―パウル・ツェラーンの「息の転回」について
◆ 第62号 (2005.4)
■中丸禎子:たそがれの物語―セルマ・ラーゲルレーヴ『イェスタ・ベルリングのサガ』における前近代的世界(後編)
■満留伸一郎:顔と形象 ―全体性についての試論:ムージル『トンカ』を中心に ―
■田中亜美:<海>のみちのり ―パウル・ツェラーンにおけるメタ詩の変遷について
■小林詩奈子:断章の書き手としてのボート・シュトラウス―『爪先立ちで下に立つもの』の言語について
◆ 第61号 (2004.9)
■中村恵美子:イロニーの原理 ―ロマン主義芸術試論
■中丸禎子:たそがれの物語―セルマ・ラーゲルレーヴ『イェスタ・ベルリングのサガ』における前近代的世界(前編)
■山崎泰孝:喪失と想起 ―リルケ『ドゥイノの悲歌』論
◆ 第60号 (2004.1)
■江口大輔:ポエジーの救出 ―ジャン・パウル『生意気盛り』について
■田中千裕:メルヒェンの文体 ―「雪白とばら紅」(KHM161)を手がかりに
■川﨑朋子:ムージルの詩学 ―『イシスとオシリス』における循環のモティーフをもとに
■時田郁子:新しい人間・熱狂者あるいは眩暈・夢想家 ―ムージル『熱狂者たち』について
■柳橋大輔:深淵に架橋する ヴァルター・ベンヤミンにおける〈媒質的なもの〉としての身体
■村瀬民子:機械の眠り ―ハイナー・ミュラー『セメント』論(Ⅱ)
◆ 第59号 (2003.6)
■畠山寛:ヘルダーリンの後期讃歌『唯一者』と固有名詞
■柳橋大輔:カメラにおける魔術 ヴァルター・ベンヤミンと媒質としての写真
■古矢晋一:アナロジーとコスモロジー ― エリアス・カネッティ『群衆と権力』
■村瀬民子:幻想の勝利―ハイナー・ミュラー『セメント』論(Ⅰ)
■由比俊行:ユートピアと牧歌の光 ― クリスタ・ヴォルフ『場所はない。どこにも』をめぐって―
◆ 第58号 (2003.1)
■畠山寛:ヘルダーリンの「聖なる名前」と『ゲルマーニエン』
■平野嘉彦:中間休止/身体―ベンヤミンとゲオルゲについての一章
■岡本和子:芸術形式としての象徴―W. ベンヤミン『ゲーテの「親和力」』を手がかりとして
◆ 第57号 (2002.7)
■桂元嗣:記憶の居場所―ローベルト・ムージルの『黒つぐみ』における語りの構造について
■岩本剛:アレゴリーという「言語」―ベンヤミン『ドイツ悲劇の根源』におけるバロック・アレゴリー論について
■Kazuko OKAMOTO: Körperliches
Erzählen―Zum Erzähler-Aufsatz von Walter Benjamin
■中丸禎子:思い出す、忘れる、生きる―ゼーガース『死んだ少女たちの遠足』における記憶のあり方
◆ 第56号 (2002.1)
■山村浩:ニーチェの『ツァラトゥストラ』に見られる人間の構造論―「自己超克」の概念をめぐって―
■岡本和子:W. ベンヤミン『ドイツ悲劇の根源』における<時間的なものの空間化>
■福間具子:具有される異性(1)― パウル・ツェランの内なる詩学
■田中亜美:声から唄へ―ツェラーンとふたつの絞首の木
◆第55号 (2000.11)
■山村浩:二つの芸術論的考察―芸術における「不可能なもの」をめぐって―
■山村浩:道徳と普遍
■満留伸一郎:限定と昂揚―『特性のない男』感情心理学とその書きかえを中心に―
■泉谷千尋:纏い替えた衣―ハルトマン・フォン・アウエ『グレゴーリウス』論
■中込雄一:ウォルフラム・フォン・エッシェンバッハ『パルツィヴァール』における語り
■大内滋:パロディー(替え歌)としての『ヘルムブレヒト物語』
■浅井英樹:ゲーテ『ヴィルヘルム・マイスターの修行時代』における身体
■清水智裕:女性と遡行―ムージル『特性のない男』のイメージ研究の試み
■福間具子:解体と生成―パウル・ツェランにおける主体と詩的言語
■西岡あかね:ゲオルグ・ハイムにおける終末の虚構(Ⅰ)
◆第54号 (1998.12)
■浅井英樹:無名の関係-ゲーテ『トルクヴァート・タッソー』をめぐって-
■山村浩:笑いについて-ホフマンスタールの『むずかしい男』-
■桜井麻美:liegen,sitzen,stehen,…の完了形構造-1200年頃の文献をめぐって-
■糸井美樹子:『クードルーン』試論-Brautwerbung:のSchemaから-
■尾張睦:生き延びるための書物―ベンヤミン『ベルリンの幼年時代』とその形式
◆第53号 (1998.6)
■浅井英樹:ゲーテ『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』における「想像力」について
■多代田いわみ:ライナー・マリア・リルケの『オルフォイスへのソネット』について
■山田光博:(私の)無、純度いつも六分前後で
■明星聖子:『批判版・〈さまざまな死〉プロジェクト』にいたる道のり-インゲボルク・バッハマンの遺稿編集の問題をめぐって-
■尾形陽子:Abgetrennter Schrei-Anne
Dudens „Der Auftrag die Liebe“-
◆第52号 (1997.12)
■坂本貴志:ゲーテの象徴論との対比でみたシラーの『プロローグ』について
■満留伸一郎:愛と魂の合一-R・ムージル「合一」論-
■量恵子:ゲーテ『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』考察
■舩木篤也:芸術と認識-ニーチェ『道徳外の意味における真理と虚偽について』をめぐって-
■小宮正安:『イェーダーマン』の時空-夢・死・寓意を巡る考察-
■石山睦:枯葉のメッセージ-カフカにおける断片的なものについて-
■佐藤陽子:継母語としてのドイツ語 多和田葉子「夜にきらめく鶴の面」における「母語」
◆第51号 (1996.11)
■坂本貴志:『ドン・カルロス』論
■小宮正安:『ナクソス島のアリアドネ』試論-その「前芝居」を中心に-
■清水智裕:ムージルの手すさび(彼の遺稿と「遺書」について)
■坂本貴志: Zur Idee der Freiheit in Schillers Ästhetik vom Schönen und Erhabenen
■明星聖子: "Der Jäger Gracchus" in der neuen Textgestalt - Die Bedeutung
und die Grenzen der "Kritischen Kafka-Aufgabe" -
■尾張充典: Empfängnis der Schrift. Zu Kafkas "In
der Strafkolonie"
■高橋完治:ムージルにおける<視線>の形
■富重純子:困難な幸福-ヨーゼフ・ロートの『偽の分銅』をめぐって-
■ 海老根剛:裂け目から裂け目へ (Benjamin)-思考と両義性あるいは翻訳と歴史に向かって
◆第50号 (1996.8)
■小宮正安:『薔薇の騎士』に於けるバロック的なもの
■西岡あかね:夢のレトリック-ゲオルク・トラークルの詩法-
■山田光博:パウル・ツェランの詩作の詩作
◆第49号 (1995.10)
■柴田翔:ゲーテ読解の視座の変遷-私的研究小史-
■柴田翔:退官に当たって
■柴田翔:驢馬と王国-ゲーテを追って迷い込んだ世界-東大退官にあたって-
■柴田翔:ゆらぐ風景-定年退官後二か月目に-
■尾方一郎:『ファウスト博士』の母たち-あるいは閉ざされた世界について-
■量恵子:『タウリスのイフィゲーニエ』試論
■栗山暢一:叙情詩の変容に関する覚書-若いハイネの場合
■柴田翔:文学研究方法私的序説あるいは山の登り方について 及びGoethe: "Über allen Gipfeln ist Ruh"を対象とした実例の試み
■SHIBATA SHÔ: Brief über die jugendlichen Schatten
und "Die Möwe" von Anton Tschechow. Dem Gangolf Schrimpf zum 60. Geburtstag.
■藤井啓司:灰色の地に灰色の文字で プレンツラウアー・ベルクと秘密警察
■永田善久:法の感性的要素-ヤーコプ=グリムの初期法論文と『ドイツ法古事誌』をめぐって
■永田善久:歴史性/超歴史性の弁証法-ヤーコプ=グリムのポエジー観
◆第48号 (1995.7)
■小宮正安:根元への誘い-ホーフマンスタールと旅-
■若林恵:生の扉の前
■尾張充典:堕落するものがたり-『断食芸人』の語り手の問題-
■富重純子:失われた"Zufall"を求めて-ヨゼフ・ロートの『タラバス』
◆第47号 (1995.6)
■縄田雄二:フリードリヒ・ヘルダーリンの視覚像-"In
lieblicher Bläue"とその後裔-
■Susumu Kuroda: Dativcausee in der lassen- Konstruktion und syntaktische
Reanalyse
■Mami Sakurai: Zur Auxiliarselektion bei der
Perfektbildung im österreichischen Deutsch
■清水真哉:ニーチェの認識論-『情動の遠近法学』-
■浅井英樹:ゲーテ『親和力』における「遅れ」の問題について
◆第46号 (1994.11)
■永田善久:グリムのメルヘンとザ-ゲにおける「言葉-遊び」-フォルクスポエジ-の様式的基底-
■高橋完治:『特性のない男』(1)
■松田正雄:ベルンハルトの>Ja<について
■Susumu Kuroda: Zur Semantik des Präsens in
der deutschen Gegenwartssprache-Ein prototypsemantischer Versuch-
■工藤達也:形象と歴史II-W・ベンヤミンの『ドイツ悲劇の根源』について-
■尾張充典:コサックダンス (二)-『うた歌いヨゼフィーネあるいはネズミの民』の場合-
■清水智裕:侵入と他者-ローベルト・ムージル『特性のない男』の運動性について-
◆第45号 (1994.7)
■尾張充典:コサックダンス(一)-『ある犬の研究』の場合-
■若林恵:逃亡者の笑い-ローベルト・ヴァルザーの『盗賊』におけるパラドックス-
■真田健司:崩壊し、結晶する言葉-ゲオルク・ビュヒナーにおける創作技法上の諸問題その1『ダントンの死』
■川嶋均:ドナウエッシンゲン受難劇の語法と構成原理
◆第44号 (1993.11)
■中島隆:A.グリューフィウスの作品にみる身体性-あるいはベンヤミン『ドイツ悲劇の根源』のいうところの「死体の産出」について
■伊東正夫:<夢想家たち>の室内-ムージルの言語空間を求めて-
■中村新:「夢」と「混沌」-初期トラークルにおける「自我」の在り方について-
■松田正雄:精神分析と文学解釈
■工藤達也:形象と歴史I-クラーゲスの形象論と初期ベンヤミンによる形象世界批判-
◆第43号 (1993.8)
■松田正雄:現代という問題-第一章リルケ『マルテの手記』-
■中島隆:<私>そして<他者>-H.E.ノサックの場合-
■石田雄一:ドイツ現代演劇における「間テクスト性」概念について
■大宮洋子:作品の内と外-『特性のない男』の構造をめぐって-
■石田雄一:オースティンの言語行為論における演劇的コミュニケーションの位置づけ
■縄田雄二:抒情的自我の概念について諸用法の概観
◆第42号 (1993.6)
■栗山暢:ラファエロの頭蓋骨あるいは旅行することの問題-ゲーテ『イタリア紀行』をめぐって-
■堀田真紀子:「愛」と「欺き」の共謀-ローベルト・ムージルの作品における媒介性の問題について(二)
■松原良輔:「囚われ」と「逃走」-クライストの『ミヒャエル・コールハース』をめぐる一試論-
■大宮洋子:統合としての女性-『特性のない男』読解の試み-
■鈴木純一: Die Struktur der Selbstreferenz und die
Systemtheorie Luhmanns
◆第41号 (1993.1)
■栗山暢:ゲーテ『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』について
■堀田真紀子:「愛」と「欺き」の共謀-ローベルト・ムージルの作品における媒介性の問題について(一)
■山口庸子:「人形たちの夢」-ネリー・ザックスの幾つかの「舞台作品」について-
■伊東正夫:<可能性>のアラベスクの戸口で-ムージルの喜劇『ヴィンツェンツとお偉方連の女友達』について-
■吉村亨:ゲルトルート・フォン・ル・フォールの『海の法廷』-表現技法に現れた救済の論理について
◆第40号 (1992.5)
■明星聖子:「判決」の行方-カフカの「書くこと」をめぐって
■尾方一郎:芸術の倫理-『ファウストゥス博士』における創造の論理 (三)
■吉村亨:「ニーチェとキリスト教」に関する覚書-パウロを中心に-
■武次玄三:<笑い>の構造-タナトス(反復強迫)としての<笑い>
■新本史斉:20世紀のメルヒェンの場所-ローベルト・ヴァルザーの『白雪姫』小論
■山口庸子:マグノリアの館(承前)-パウル・ツェランの「我」-
◆第39号 (1991.11)
■清水譲:盲目と狂気-クライスト試論『シュロッフェンシュタイン家』を中心に-
■尾方一郎:二十世紀のファウスト-『ファウストゥス博士』における創造の論理(二)-
■西村龍一:同一性の中の時間-ヴァルター・ベンヤミンの言語哲学と構造主義言語学-
■田中昭夫:中高ドイツ語のze不定詞とhan
■鈴木純一:ベンヤミンの『ドイツ・ロマン派における芸術批評の概念』における芸術批評の概念
■伊東正夫: Stimmen aus dem Stummsein-in Hofmannsthal
- Strauss' >>Ariadne auf Naxos<<
■武次玄三:制度批判のドラマトゥルギー-エルヴィン・ピスカートアのヴァイマール時代後期の演出作品の分析-
◆第38号 (1991.9)
■中島隆:グリンメルスハウゼン『ジンプリチスムスの冒険』における肉体と虚構と妄念と
■真田健司:自由への<試戯>-ゲーテ『エグモント』における運命の問題-
■尾方一郎:物語の時空-『ファウストゥス博士』における創造の論理 (一)-
■松原良輔:類似、模像、比喩-アイヒェンドルフの『予感と現前』をめぐって-
■山口庸子:マグノリアの館-パウル・ツェランの「我」-
■清水譲:Fliegende Fluchtpunkte-Noten zu Husserl-
◆第37号 (1991.6)
■吉村亨:仮面・変身・衣装-ニーチェ論の試み-
■石田雄一:ブレヒトの "Gestus" 概念に見られる「演出」の位相-19世紀末以後の演劇批評と言語哲学-
■園田みどり:侏儒の回廊-ボートー・シュトラウスの『青年』における<Zeit-Geist>(時代の精)-
■縄田雄二:ヘルダーリン作"Patmos"終結部の解釈について
■秋葉篤志:溶ける卵-ハンス・アルプの詩-
■大豆生田淳子:浄められた秋 (下)-トラークルにおける「滅び」の問題-
◆第36号 (1990.12)
■縄田雄二:ヘルダーリン作「希望に寄す」「励まし」「メノーンの嘆き」-三詩の成すチクルス-
■吉原素子:グリム兄弟の手本-ルンゲ兄弟の「漁師とその妻の話」-
■石田雄一:精神分析的観点から見た叙事的演劇
■大豆生田淳子:浄められた秋(中)-トラークルにおける「滅び」の問題-
■宮川栄司: H.v.ホーフマンスタール『第六百七十二夜のメルヒェン』(承前)-そのテクストの完全解明へ向けて-
◆第35号 (1990.10)
■伊東正夫:チャンドス卿の<現在>-ホフマンスタールにおける意識と言葉をめぐって (下)-
■宮川栄司:H.v.ホーフマンスタール『第六百七十二夜のメルヒェン』-そのテクストの完全解明へ向けて-
■大豆生田淳子:浄められた秋 (上)-トラークルにおける「滅び」の問題-
■清水朗:Der arme truhsaeze-あるいはケイエ卿に捧げるオマージュ-
■井出万秀:動詞lassenの用法に関する考察 (3)-「Kausativ体系」の中でのlassen-
■清水穣: >>Différance und Transfinitum<<
Bemerkungen über das Problem der aktualen Unendlichkeit
◆第34号 (1990.6)
■伊東正夫:チャンドス卿の<現在>-ホフマンスタールにおける意識と言葉をめぐって(上)-
■鈴木純一:トーマス・マンにおける自己言及のシステム
■石井道子:留保された教訓-WaltherとReichston 第一部 L.8,4について-
■石井道子:ある隠者-WaltherとReichston L.9,16-
■阿部卓也:カント『啓蒙とは何か』への註-分割と迂回-
■清水穣:Das Mosaik Stifters
◆第33号 (1989.9)
■宮川栄司:自然搾取と原始志向(承前)-フリードリヒ・ヘルダーリンにおける自然と人為の問題についての包括的考察-
■秋葉篤志:焼尽される符徴-パウル・ツェランの後期の詩-
■内村博信:記憶と痕跡-パウル・ツェラン-
■田中昭夫:中高ドイツ語のze不定詞とsîn
■石井道子: wie stêt dîn ordenunge!-WaltherのReichston L.8,28-
■武次玄三:<笑い>の構造-カール・ヴァレンティンの場合-
◆第32号 (1988.11)
■瀬川裕司: J・アメリーの『映画日記』あるいは反=<特権的>なる映画の鑑賞法について
■西村龍一:語ることと始源-フランツ・カフカの目-
■高田里恵子:劇中劇はどこに隠れているか-ペーター・スローターダイク『魔の木』を手がかりとして-
■新野守広:裸形の夢-初期ムージルにおける身体のイメージについて-
■南剛:ノイトラール[中性的]な個別現実性と世界をえぐる<仮象>(承前)-『ヨゼフとその兄弟たち』試論-
■山田積:ノヴァーリス『ハインリヒ・フォン・オフターディンゲン』における<火>と<水>
■井出万秀:動詞lassenの用法に関する考察 (2)-lassen-文の意味解釈-
◆第31号 (1988.5)
■足立典子:現実と文学-アレクサンダー・クルーゲの『一九四五年四月八日のハルバーシュタットの空襲』について-
■市田せつ子:リルケの『時祷詩集』-「生」「神」の獲得-
■松永美穂:「あり得た過去」としてのユートピア-シュテファン・ハイムの『シュヴァルツェンベルク』を中心に-
■孟真理:夢想と現実-トーマス・マンの初期短篇における現実意識とその表現-
■宮川栄司:自然搾取と原始志向-フリードリヒ・ヘルダーリーンにおける自然と人為の問題についての包括的考察-
■井出万秀:動詞lassenの用法に関する考察(1)-問題点概観-
◆第30号 (1987.6)
■南剛:ノイトラール[中性的]な個別現実性と世界をえぐる<仮象>-『ヨゼフとその兄弟たち』試論-
■河野みどり:ローベルト・ムージルの『生前の遺稿集』における「死」へのただならぬ執着
■西村龍一:根拠としての牧歌-カフカの『アメリカ』-
■境一三:シェリングにおける自然の回復-神々を求めて-
■足立典子:G・ヴァルラフのルポルタージュについて-文学と虚構-
■柴泰介:トーマス・ベルンハルト小論
◆第29号 (1986.12)
■松永美穂:クリスタ・ヴォルフの文学における夢とヴィジョン
■阿部卓也:悲劇の誕生-あるいは虚構について-
■河野みどり:いたずらの庭-ローベルト・ムージルの『特性のない男』について-
■小菅路子:メールヒェン『蚤の親方』について-E.T.A.ホフマン晩年のフモール観-
■武井隆道:『西東詩集』の考察
■越谷直也:シュライエルマッハーの「対話的精神」-『独白録』をめぐって-
■渡辺伸治:ドイツ語移動動詞kommenにおけるダイクシス特性中立化について
◆第28号 (1986.11)
■久保哲司:「神学」から「人間学」へ-中期ヴァルター・ベンヤミンにおける「世俗化」過程についての一考察-
■杉野里恵子:喜劇に於ける劇中劇の構造その(二)-グリューフィウスからティークへ-
■清水本裕:ニーチェ研究における文学者としての立場-「著作」と「遺稿」の取り扱いをめぐって-
■武井隆道:ゲーテ作『トルクヴァート・タッソー』の考察
■清水朗: Mhd.動詞結合価と属格補足成分-与格あるいは対格と共起する場合に関して-
■清水朗:Mhd.格体系についての一考察-属格を伴う"lexikalische Fügungen"を中心として-
◆第27号 (1986.9)
■境一三:初期フリードリヒ・シュレーゲル研究-「実在的なもの」そして「客観的なもの」-
■反町裕司:『クライストの二つの喜劇』
■久保哲司:思考のロゴスとエートス-初期ヴァルター・ベンヤミンの批評理論の形成におけるその言語観・認識観・真理観 (一)-
■瀬川裕司:ペーター・ハントケ「ゴールキーパーの不安」を巡って
■武井隆道:シュティフターの『石さまざま』について-細部と全体の空間構造的意味-
◆第26号 (1986.6)
■松永美穂:明日を拒んだ女-ヴォルフ『カサンドラ』におけるアルタナティーヴェとユートピア-
■瀬川裕司:オスカル・マツェラートあるいは倒錯した貴公子-専ら主人公論としての「ブリキの太鼓」へのアプローチ-
■藤井啓司:歴史の此岸・歴史の彼岸-戦後アンナ・ゼーガースの軌跡-
■相沢啓一:「戦後文学」の希望と限界-アルフレード・アンデルシュにおける政治と文学 (二)-
■石井正人: QuesteとZühte-Wolframの"Selbstverteidigung" について-
■村上公子:ドイツ語の二人称代名詞-親称と敬称の変遷-
■石井正人:鷹、梟、そして鸛-Walter-Reinmar-FehdeとWolfram-
◆第25号 (1985.12)
■富重与志生:ハルテンベルクの時空-その(一)-
■瀬川裕司:擬態としての文学-「ブリキの太鼓」の語りにおける仕掛けの諸相-
■石井正人: Carmina Buranaにおける中高ドイツ語詩
■石井正人: Nova Carmina - Walther-Reinmar-Fehde -
◆第24号 (1985.6)
■久保田聡:逡巡する精神-トーマス・マンの『ヨゼフとその兄弟たちへのひとつの考察』-
■松永美穂:クリスタ・ヴォルフ『幼年期の構図』-物語空間の可能性-
■反町裕司:クライストの作品における人間の生
■高山秀三:青年期のトーマス・マン
■越谷直也:ゲーテにおける憧憬の諸相
■武井隆道:ゲーテの建築論について
■木下直也:1910~12年のカフカ(二)-『判決』あるいは距離の発見-
■渡辺学:フンボルトの「内的言語形式」再考
◆第23号 (1984.11)
■日中鎮朗:ゴットフリート・ベン「医師レンネ論」-その世界認識の構造-
■前田良三:パリのめぐりあい-それともBとともに逃げるC-
■足立信彦:文学の歴史性-その問題点の展望-
■木下直也:1910~12年のカフカ(一)-「書けない」と書くことあるいは「力の過剰」 Überschuß der
Kräfte-
■村上公子:「ファウスト」第二部における二人称の使用(承前)
◆第22号 (1984.7)
■相沢啓一:二つの『ルーフ』をめぐって-アルフレート・アンデルシュに於ける政治と文学 (1)-
■杉野里恵子:不透明性と同質性の演劇-続・受動的道化たちの悲喜劇-
■田畑雅英:ティークのメルヒェンにおける昼と夜
■高山秀三:トーマス・マンの『告白』
■境一三:初期フリードリヒ・シュレーゲル研究-「ことば」と「イロニー」をめぐって-
■高山秀三:<<チリの地震>>の構造
■木下直也:縮小する地図-カフカの小文学(kleine
Literatur)について-
◆第21号 (1983.12)
■足立信彦:『特性のない男』におけるモティーフ「別の状態を解釈する試み」
■杉野里恵子:受動的道化たちの悲喜劇-ゲオルク・ビューヒナーの劇-
■杉野里恵子:喜劇に於ける劇中の構造その1-J.M.R.レンツの場合-
■田畑雅英:ティークの初期作品の人物像-『カール・フォンベルネック』の場合-
■日中鎮朗:変身」に於ける視点と技法-思考の発動機制の転機-
■高橋慎也:夢のゆくえ-第一次世界大戦のホーフマンスタール-
■木下直也:カフカの時代とその歴史的言語状況-書くことの悪魔性について-
■村上公子:「ファウスト」第二部に於ける二人称の使用(承前)
◆第20号 (1983.6)
■日中鎮朗:フランツ・カフカ「城」の諸相-テクスト固定から解釈へ-
■藤井啓司:『第七の十字架』への道-芸術の光に照らし出された「あたり前の生活」について-
■渡辺学:記号・象徴・言語-ヴィルヘルム・フォン・フンボルトの場合-
■前田良三:<水>の詩学(承前)-パウル・ツェランにおける詩的想像力について-
■Keiichi AISAWA: IRONIE UND MUSIK THOMAS MANNS "DOKTOR
FAUSTUS"
■村上公子:「ファウスト」第二部に於ける二人称の使用(承前)
◆第19号 (1983.1)
■識名章喜:<<アトランティス>>の行方-E.T.A.ホフマンの「メルヘン」について-
■高橋慎也:第一次世界大戦とホーフマンスタール-「オーストリア」の夢の崩壊-
■前田良三:<水>の詩学-パウル・ツェランにおける詩的想像力について-
◆第18号 (1982.9)
■三宅晶子:「経験の貧困」の時代における「経験」の叙述-後期ヴァルター・ベンヤミンの思想-
■市岡正適:エーリッヒ・ケストナーにおける意識の基本的様相
■山下敦:調和を引き裂く力-ヘルダーリン後期の思考様式と自由律讃歌-
■赤司英一郎:ローベルト・ムージルの方法についての幾つかの考察
■村上公子:「ファウスト」第二部に於ける二人称の使用(承前)
■木下直也:カフカ論 (2)-判決Das Urteilを読んでみる。-
◆第17号 (1981.10)
■三宅晶子:ヴァルター・ベンヤミンにおける「経験」形成の願望
■山下敦:へルダーリンにおける詩の場の構造と宥和をもたらす歌の虚偽性vsうたのもつ破壊性・断片性について
■市岡正適:孤独の対話-ホルバートに沿って-
■赤司英一郎:ローベルト・ムージルの方法についての幾つかの考察
■村上公子:ゲーテ「ファウスト」第二部に於ける二人称の使用(承前)
■土合文夫:ホーフマンスタールにおける「社会的なるもの」をめぐって
◆第16号 (1980.9)
■前野みち子:ハインリッヒ・フォン・クライスト-その作品世界の成立をめぐって-
■河口憲子:神々の探索-「セチュアンの善人」考-
■前田良三:失われた<喪失>-パウル・ツェランの狭さ-
■前野みち子:彼岸の消息(承前)-ハンス・エーリヒ・ノサック論-
■村上公子:ゲーテ「ファウスト」第二部に於ける二人称の使用
■木下直也:カフカ論 (1)-語る主体と言語の空間-
■山本有子:ゲーテ「古典主義」期の歴史意識
◆第15号 (1980.4)
■水上藤悦:詩劇の可能性-世紀末詩劇の生成に関する覚え書き-
■河口憲子:Komikの生成-ビュヒナー断想-
■前野みち子:彼岸の消息-ハンス・エーリヒ・ノサック論-
■松浦純:エラスムス--ルター論争とルターの所謂「隠れたる神」
■毎熊佳彦:ニーチェにおける祝祭の構造(承前)
■Kimiko Murakami: Zur Komplementation in der
deutschen Sprache (Fortsetzung)
◆第14号 (1979.6)
■山下有子:ゲッツとヴァイスリンゲン-ゲーテ初期の歴史的思考の発展-
■毎熊佳彦:ニーチェにおける祝祭の構造
■Jun Matsuura: Die Versprachlichung der
Verdinglichung der Versprachlichung: Zu Peter Handkes "Der Rand der Wörter
2"
■Kimiko Murakami: Zur Komplementation in der
deutschen Sprache.
◆第13号 (1978.12)
■浅井健二郎:Kの肖像
■谷本慎介:『悲劇の誕生』(Fr.ニーチェ)について-その自然観と自我観-
■北彰:海・道化、そして精神-トニオ・クレーガー小論-
■大友進:『ザイスの学徒達』による>>小説<<の研究
■重藤実:変形規則への制約と展開値
◆第12号 (1978.7)
■清水本裕:ニーチェに於けるアポロ的倫理とディオニュソス的美学
■大友進:『ハインリッヒ・フォン・オフターディンゲン』>>芸術的精神<<の>>現象学<<-その構成と解釈-
◆第11号 (1977.12)
■北彰:保守的想像力-トーマス・マン「非政治的人間の考察」-
■檜山哲彦:子午線の生理(承前)-パウル・ツェランの詩-
■若松準:ベンヤミンのヘルダーリン解釈について
■小林正幸:シラー『ヴァレンシュタイン』試論
◆第10号 (1977.6)
■平山令二:『賢者ナータン』試論-寓話・歴史・寛容-
■檜山哲彦:子午線の生理-パウル・ツェランの詩-
■福本義憲:音韻変化の時間性と空間性
◆第9号 (1976.12)
■谷本慎介:「心」の作品世界
■原研二:冷たい花嫁たちの国-カール・クラウスに於ける風景
■浅井健二郎:根拠への試み - H・ブロッホの「ヴェルギリウスの死」について (2) -
■早坂七緒:ムージルのマッハ論文-紹介と評価の試み(承前)-
◆第8号 (1976.6)
■檜山哲彦:愛に向かって〔詩〕
■水上藤悦:世紀転回期の世代-リルケのベンヤミン-
■原研二:自画像を駆めぐるもの- K・クラウスに於ける風景への序論 -
■浅井健二郎:<まなざし>の立つトポスとしての境界空間
- H・ブロッホの「ヴェルギリウスの死」について(1) (承前)
■福本義憲:アナロジーの条件
■壱岐七涛:ビュヒナー雑感
◆第7号 (1976.1)
■浅井健二郎:<まなざし>の立つトポスとしての境界空間
- H.ブロッホの「ヴェルギリウスの死」について (1) -
■鍛治哲郎:表現主義覚え書 (1)-過程としての表現主義-
■水上藤悦:運命のない詩人-リルケ試論-
■早坂七緒:ムージルのマッハ論文-紹介と評価の試み-
◆第6号 (1974.12)
■斉藤松三郎:ローベルト・ムシル『特性のない男』-試論その一-
■若松準:ヘルダーリン『ムネモシュネー』について
■今泉文子:>>Unsagbares zu sagen<<-ノヴァーリスとフランクフルト学派をつなぐ批評の精神を求めての端緒的試み-
◆第5号 (1974.9)
■浅井健二郎:トポスへの試み
■水田恭平:読むこと・書くこと
■吉岡義彦:認識と形象化-トーマス・マン論その一-
◆第4号 (1973.12)
■今泉文子:「万物照応」の論理-ノヴァーリスにおける魔術的なるものをめぐって-
■青木誠之:"制禦するもの"-ヘルダーリン素描-
■谷川道子:ブレヒトと表現主義その一-ブレヒト演劇の生成と表現主義-
■斉藤松三郎:狂った磁気-解像と表現について-〔創作(戯文)〕
◆第3号 (1966.12)
■平子義男:「世界空間をはらんだ風」
■西山力也: Über Goethes "Wilhelm Meisters
Lehrjahre"
■岩切正介:ニーチェの中期
■根本萠騰子:「アンリ4世」の評価 (続)
■岩切正介:トーマス・マンの「ヨーゼフとその兄弟たち」
■東郷日出男(特別寄稿):「時代の転回と詩人」考
◆第2号 (1966.6)
■坂田正治:抵抗の詩人たち
■樋口大介:「変身」-おぼえがき-
■森光昭:ブレヒト演劇における感情の位置
■恒川隆男:時間と美
■小松英樹:カフカの世界観
■根本萠騰子:「アンリ四世」への評価のこころみ
■佐藤信行:精神の冒険者たち(2)・トラークル-絶望のなかで歌う焔-
◆第1号 (1966.1)
■佐藤信行:精神の冒険者たち (1)-「人類の曙」の詩人たち・ハイム-
■岩切正介:「ある詐欺師の回想」(トーマス・マン)に於けるパースペクティヴ
■船戸満之:時代の転回と詩人-ルカーチ論の試み (1)-
■中世ドイツ文学研究会:初期のミンネザング
■小栗友一:ラインマル・フォン・ハーゲナウとヴァルター・フォン・デル・フォーゲルヴァイデの対立に関する一考察
■井上修一:タシケントの風船売り
■吉島茂:DER GOTISCHE OPTATIV IN NEBENSÄTZEN - in Bezug auf das Tempus -